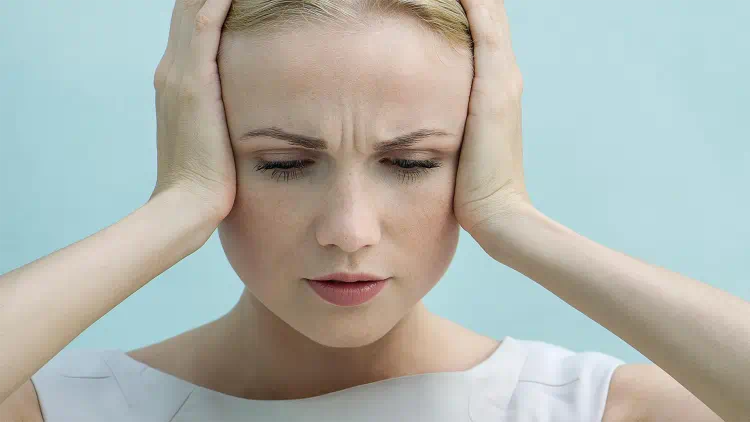思考や行動、人が生きていくために必要なすべての判断を行うのは脳です。しかし、普段は指令を出す立場にある脳も、身体的・精神的な症状によってその活動が鈍くなることがあります。
脳の活動に影響を及ぼす身体的な症状のひとつが難聴です。難聴は年齢や人種に関係なく誰でもなる可能性があり、これまで難聴が脳に与える影響について数多くの研究が行われてきました。
その中で興味深い研究結果がいくつかありますが、特に注目されているのが「神経の可塑性(かそせい)」という現象です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、実際にはそれほど複雑な話ではありません。
●脳は生涯を通して変化している
神経の可塑性とは、新しい機能や状況に対応しようとする脳が、神経回路の再構築を行うことを指します。

人間の脳内では、神経細胞が電子回路のようなネットワークを形成し、情報を伝達しています。しかし、電子回路と異なる点は、脳がさまざまな環境に適応し、神経細胞の接合部分(シナプス)の働きを調節することで、情報の伝達のしやすさを変化させることができるという点です。
私たちの記憶や学習を司るのは「神経の可塑性」です。自転車に乗れるようになったり、勉強して英語が話せるようになったり──このように私たちが新しいことを覚えたり、練習によって上達したりする過程で、脳は活性化され、機能や構造が変化します。このような脳の変化を「可塑性」と呼びます。
一方、「神経の可塑性」によって、使われない部分は退化してしまう、という困った面もあります。人間の体は不思議なもので「この器官はあまり使わないから不要なんだ」と脳が判断すると、その器官は退化していくと言われています。
●難聴の場合、神経の可塑性はどのように働くか
難聴者の脳で何が起きているかを簡単に説明すると、以下のようになります。
難聴になると、音から得られる感覚が弱くなるため、脳はその失われた感覚を補おうと過剰に働きます。聴覚が衰える分、視覚や触覚などを鋭くしようとします。しかし、この補償作用が強すぎることで、私たちはいつも以上に疲れを感じたり、集中力が低下したりします。
もちろん、神経の可塑性のおかげで、難聴者は聴覚の低下にある程度は適応できますが、その機能が過度に働くことで、脳に悪影響が及ぶこともあります。例えば、聴覚が低下すると、脳は「聴覚から得られる情報を理解し、思考する」という本来の能力をあまり使わなくなり、結果的に脳が劣化していくことがあります。
難聴と認知機能の関係
難聴は認知症の危険因子です。2020年、世界的医学誌LANCETで「アルツハイマー病協会国際会議」の総説が発表されました。認知症のリスクを上昇させる要因の中には、予防可能なものがあり、その中で一番大きなものが、「難聴を放置すること」であると報告されました。
聴覚情報は、さまざまな感情を引き起こす非常に重要なものです。会話のコミュニケーションは、まず耳に言葉が入ることから始まります。耳で言葉を聞き、脳でそれを処理し、言葉で返すというのが会話時の基本的なプロセスです。つまり、聴覚は思考を行うための重要な情報源であり、この聴覚によって「楽しい」「うれしい」といった感情が引き起こされます。したがって、聴覚はコミュニケーションを円滑に行うためには欠かせないものです。
難聴があるからといって必ずしも認知症になるわけではありませんが、難聴が原因でコミュニケーションが減少したり、社会との関わりが少なくなったりすることが、認知機能に影響を及ぼす可能性があるのです。
厚生労働省の最新調査結果
2024年5月8日に開催された「第2回認知症施策推進関係者会議」において、厚生労働省の研究班から認知症に関する最新調査結果が発表されました。日本の2040年時点の認知症者数が約584万人、軽度認知障害(MCI)※の人数が約613万人となると推計されています。高齢者のおよそ15%、6.7人に1人が認知症を発症し、軽度認知障害を含めるとさらに割合が増えますね。

※軽度認知障害(MCI)とは
厚生労働省の調査では「軽度認知障害」という言葉が注目されています。軽度認知障害はなかなか聞きなれない言葉ですが、MCI(mild cognitive impairment)ともいいます。認知症そのものではありませんが、しかし記憶力や注意力などの認知機能に軽度の低下がみられ、「認知症の前段階」という注意が必要な状態です。
MCIを放っておくと認知症に進行する可能性がありますが、適切な予防をすることで健常な状態に戻る可能性もあります。
社会的活動に参加したり、家族も含めた他者とコミュニケーションをとったりすることで、MCIを認知症に悪化させないよう、脳の活性化が期待できるといわれています。
■軽度認知障害(もの忘れの自覚があり、記憶力が軽度低下した状態)
■認知症(認知機能が低下した状態。もの忘れの自覚がない場合もあります)
難聴は早めの対策がいい理由
ほとんどの場合、難聴は徐々に進行します。そのため、特定の音が聞こえなくなったことに気づかず、「自分は難聴だ」と自覚するタイミングが遅れることが多いです。脳は音が聞こえにくくなっても、しばらくの間はその音の記憶を保持しますが、数年が経過するとその記憶を完全に忘れてしまいます。
音を聞くことは、脳内の聴覚神経を刺激します。この刺激があることで、脳は他の感覚を鋭くする必要がなくなり、聴覚から得られる情報を使って思考を深めるという高次機能が継続して働きます。
難聴の対処は、早ければ早いほど効果的ですが、多くの難聴者はなかなかそのことに対処しようとしません。自分が難聴だと認めたくないという気持ちがあるかもしれませんが、難聴を数年放置すると、脳にかなりの変化が生じてしまうことがあります。
解決策は、本人の意識と早めのケアです。自分が難聴だと感じていなくても、定期的に聴力検査を受けることをお勧めします。また、気になることがあれば早めに耳鼻科の医師に相談しましょう。
補聴器センター辻の無料聴力測定もご利用いただけます。医師の診察に代わるものではありませんが、予備的な判断材料として役立つはずです。